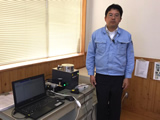廃棄物処理施設の火災対策 ~明日は我が身。「防ぐ」ための現場のリアル~

近年、廃棄物処理施設や収集運搬車での発煙・発火事故は、もはや「時折起こるトラブル」ではなく、「日常に潜む重大リスク」として業界全体の深刻な問題となっています。
環境省の発表によれば、令和5年度の発煙・発火を含む発生件数は21,751件に上り、過去最多を更新しました。このうち、リチウムイオン電池が原因とみられる火災事故は8,543件。これは全体の約4割を占め、消防隊による本格的な消火活動が必要となった「重大火災」も84件発生しています。
「うちはリチウムイオン電池の受け入れを禁止しているから大丈夫」
「現場作業員がしっかり目視選別しているから問題ない」
そう思われるかもしれません。
しかし、現実は非常に厳しく、先日開催された「一般社団法人日本RPF工業会第9回安全大会」では、「もはやどの施設でも起きうるリスクであり、明日は我が身と考えざるを得ない」と、強い警鐘が鳴らされました。
今回は同大会で報告された生々しい事例と具体的な対策をもとに、廃棄物処理施設における火災の実態と、これからの時代に求められる「本当に機能する対策」について、深く掘り下げていきます。
第1章:火災はどこで起きているのか? – 41%が集中する「破砕ライン」の恐怖
同大会では、会員企業48社(回答率68.6%)から寄せられたアンケート結果が報告されました。92件の回答のうち、実際に「火災」を経験したのは22件。その発生場所は、衝撃的なほど偏った結果となりました。
火災事例分類(全22件)
・破砕ライン(破砕機~供給設備):41%(9件)
・成形ライン :14%(3件)
・原料保管場所:14%(3件)
・RPF(製品):9%(2件)
・車両 :9%(2件)
・その他:9%(2件)
・前処理:4%(1件)
実に4割以上の火災が「破砕ライン」に集中しています。これは、多くの事業者が日々直面している現実と一致するのではないでしょうか。
リチウムイオン電池が破砕機で衝撃を受け、ショート・発火するのは典型的なパターンです。しかし、脅威はそれだけではありません。大会では、以下のような「隠れた発火物」も原因として挙げられました。
ボタン電池:プラスとマイナスが非常に近く、破砕時の衝撃で簡単にショートします。さらに厄介なのは、ショートして内部のプラスチックを静かに燃やしながらコンベアで運ばれ、後工程で「時限爆弾」的な火災を引き起こすことです。
スプレー缶・ライター:LPGガスが充満した状態で破砕機の金属接触(メタルタッチ)による火花が出れば、即座に爆発的な燃焼を引き起こします。
乾電池:複数本が重なることでショートしやすく、これもまた発火源となり得ます。
これら全てを選別で100%取り除くことは、現実的に不可能です。破砕機は常に火災のリスクと隣り合わせなのです。
さらに、リスクは破砕ライン以外にも潜んでいます。
・RPF成形ラインでは、スクリューの不具合による摩擦熱での発火事例
・重機のDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)の再生作業中に高温になり発火した事例
・破砕機本体では、操業停止後、軸部分に付着・癒着したプラスチック粉塵が「蓄熱」し、無人時間帯に自然発火した事例
も報告されており、工場全体がリスクにさらされていることがわかります。
第2章:なぜ消せない? – 廃棄物火災が「制御不能」に陥る6つの理由
「ボヤが出ても、すぐに消せばいい」そう考えるのは早計です。大会の事例報告では、発火が「被害甚大な火災」へと拡大する恐ろしいプロセスが共有されました。
一度火の手が上がると、廃棄物処理施設の火災は、消火のプロである消防隊をもってしても鎮圧が非常に困難です。その特有の理由として、6つの項目が挙げられました。
1. 火元の特定が困難
廃棄物が山積みになっており、火は内部で燃え広がるため、どこが火元か分からない。
2. 内部でくすぶり続ける(再燃)
廃棄物の山は酸素が供給されにくく、内部でくすぶり続け、見た目が鎮火しても、内部の蓄熱や、重機で廃棄物を動かした際の酸素供給で容易に再燃する。
3. 複雑な設備構造
破砕機やコンベア、原料ピットなどが障壁となり、消防隊が火元に近づけず、放水が届かない。
4. 二次災害のリスク(安全確保の制約)
可燃性ガスや有毒ガスが発生し、爆発の危険性もあるため、安全を確保しないと消防隊も現場に突入が出来ない。
5. 施設構造上の問題
様々な機械設備が複雑に入り組んだプラント構造、選別機内部の密閉された空間などが、効果的な消火活動の妨げになる。
6. 高い延焼リスク
粉塵が舞う環境では粉塵爆発のリスクがあり、何よりコンベアが炎の「運搬装置」となって火災を次々と拡大させてしまう。
第3章:被害の実態 – 「工場全焼」「被害額3億」の生々しい現実
「もし火災が起きたらどうなるのか?」その問いに対する答えは、想像を絶するものでした。
事例1:炎がコンベアで「運ばれる」恐怖
ある工場では、トロンメル(回転式ふるい機)内部で発火しました。最初は小さな火種でしたが、最悪なことに、火が付いた廃棄物がそのままコンベアで次工程へ「運搬」されてしまったのです。従業員が気づいた時にはすでに炎が別箇所で燃え広がっており、慌てて消火器で対応しようとしました。しかし、次から次へと燃える物がライン上を流れてくるため、完全に制御不能に。
さらに深刻だったのは、従業員が目の前の火を消すことに必死で、ラインを止めるための「非常停止ボタン」を押す意識が飛んでしまったことでした。火を目の前にした人間の心理として、パニックになったり、逆にアドレナリンが出て炎に突っ込んでしまったりと、正常な判断ができなくなるのです。
事例2:無人時間帯を襲う「時限爆弾」
火災は操業中にだけ起こるのではありません。ある事例では、前日の夕方に破砕した廃棄物をヤードに保管して作業を終了。しかし、翌日の早朝4時、無人の時間帯に煙が上がり、発火。保管されていた廃棄物の内部で、リチウムイオン電池が時間差で発火したと見られています。また、別の工場では、深夜1時過ぎ、プラント停止から3時間以上経過した破砕機の「軸」の部分から出火しました。これは、日中の稼働で軸に付着・癒着したプラスチック粉塵が熱を持ち続け、無人時間帯に「蓄熱」によって自然発火したと見られています。
被害の総額:失うのは設備だけではない
こうした火災がもたらす被害は、単に「機械が燃えた」という話では済みません。ある事例では、リチウムイオン電池が原因とみられる火災で建屋や設備が焼損し、被害額は約3億円に達しました。
別の事例では「工場全焼」という最悪の事態も報告されています。
設備の復旧には「半年かかった」という報告もあり、その間の操業停止による売上損失は計り知れません。
さらに、消火後は行政への報告・対応、近隣住民への謝罪、そして顧客との契約見直しや信頼の喪失といった、目に見えない甚大な二次被害が経営を圧迫します。
第4章:現場の死闘 – 地道な「アナログ対策」と「デジタル対策」
では、こうした深刻な火災に対し、現場ではどのような対策が行われているのでしょうか。アンケートや取材報告では、地道なアナログ対策から最新のデジタル対策まで、多様な取り組みが紹介されました。
1. アナログ対策(人・運用で防ぐ)
まずは、設備投資をせずとも実行できる、基本の徹底です。「火災は起こるもの」という前提に立ち、日々の運用を見直すことが重要です。徹底した清掃:
「蓄熱火災」を防ぐため、破砕機周辺や軸部分など、粉塵や癒着物が溜まりやすい箇所の終業時清掃を徹底します。
五感を駆使した点検:
原料の荷下ろし時、破砕後の展開検査といった目視確認はもちろん、重機の電気系ハーネスの損傷や焦げ臭い「臭い点検」、重機のDPF燃焼中の監視を強化します。
死角をなくすレイアウト:
原料投入場所から破砕機、成形機までをオペレーターが常時目視できるよう、ラインを「L字型に配置」するといった工夫も有効です。
実践的な防災訓練:
「消火器がどこにあるか」を全員が即答できる体制を整えます。例えば、高所火災の場合、下からホースを運ぶと1分半かかりますが、上からホースを落として途中で連結すれば1分で対応できる、といった具体的な時間短縮訓練も行われています。
BCP(事業継続計画)の策定:
万が一の設備停止に備え、落雷で基盤が故障した(復旧に半年かかった)事例の教訓から、モーター、減速機、基盤などの重要予備品をあらかじめ確保しておくことも、事業継続の観点から極めて重要です。
2. デジタル対策(機械・システムで防ぐ)
人の力だけでは限界がある「検知」と「初期消火」を、テクノロジーで補います。監視カメラ・温度センサー:
オペレーターから死角になるヤードを監視カメラで常時確認し、事務所のモニターで監視する。また、破砕機の下部シュートなど、発熱しやすい箇所に温度センサーを設置し、異常を検知します。
炎センサー(火炎検知器):
最もリスクの高いコンベアの乗り継ぎ箇所や破砕機出口、ヤードにピンポイントで設置します。ある工場では、初期の7個から段階的に増設し、現在は41個の炎センサーで工場全体を監視している事例も報告されました。
局所的な消火設備:
コンベア上部へのミストシャワー、ライン各所への手動散水バルブ、冷却塔内への散水装置など、火元となり得る場所に消火設備を増設します。破砕後の受けをあえて鉄製のバッカンにし、発火してもその中で燃え止まらせ、バッカンごと場外に運び出して鎮火するという運用も有効です。
第5章:火災対策の新常識 – 「消す」から「防ぐ」へ。自動初期消火システム
ここまでの対策は、「火災の発生」または「被害の拡大」をある程度許容するものでした。しかし、リチウムイオン電池火災が激増する今、求められているのは「発火の瞬間に、自動で検知し、自動で停止し、自動で消火する」という、より能動的な「被害ゼロ」を目指すシステムです。
大会では、複数の企業から先進的な自動初期消火システムの事例が紹介されました。
従来型スプリンクラーでは「間に合わない」という現実
消防法で定められた従来型のスプリンクラーは、多くの場合「熱」や「煙」を感知します。しかし、これは「炎が天井近くまで上がってから」作動することを意味します。その時点では、すでにコンベアで火が運ばれた後かもしれません。また、一度作動すると施設全体が水浸しになり、消火用水が枯渇すれば再出火に対応できません。被害額3億円の事例もあったように、火災そのものより水損による操業停止(復旧に数ヶ月かかることも)のダメージが甚大になるケースも少なくないのです。
求められる「3つの自動化」
先進的なシステムは、この従来型の弱点を克服するために設計されています。1. 高速検知(炎):
熱や煙ではなく、「炎」そのものを高速(例:AIが0.05秒)で検知します。10mm程度の小さな炎でも検知が可能です。
2. 自動停止(ライン):
炎を検知した瞬間、即座に破砕機やコンベアを「自動停止」させます。これにより、炎の「運搬」を物理的に遮断します。
3. 自動・局所放水:
施設全体ではなく、検知したエリア(火元)にだけピンポイントで自動放水します。炎が消えれば自動で停止し、水の枯渇を防ぎます。もし再燃しても、再度検知して放水します。
ある企業では、この自動初期消火システムを導入後、リチウムイオン電池による発火は何度も経験しているものの、一度も操業停止に至る火災にはなっていないと断言しています。別の企業では、このシステムが「1日に3回発報するが、その都度自動で対応し、事故ゼロを継続している」という、いかに火災リスクが日常的であるかを示す生々しい運用実態も報告されました。
さらに、AIによる画像認識、無線配線による導入の容易さ、監視室での状況可視化、各工場の実態に合わせたカスタマイズなど、システムは日々進化しています。ある先進事例では、このシステムを警備会社と連携。無人時に自動放水が作動すると、貯水タンクの水位低下を警備会社が検知し、自動通報される仕組みを構築しています 。これにより、発煙から消防隊の活動開始まで「46分」かかっていた(かもしれない)火災を、タイムラグゼロで初期消火できる体制を整えています。
結論:アナログとデジタルの両輪。「経営を守る投資」として今すぐ行動を
本大会で共有された数々の事例は、廃棄物処理施設における火災が、もはや「避けられないリスク」であることを突きつけています。排出事業者への分別協力依頼や、現場での目視選別には限界があります。
私たちにできることは、「火災は起こるもの」という前提に立ち、万が一発火しても、「被害を最小限に抑え込み、操業を止めない」体制を構築することです。
地道な清掃や実践的な訓練といったアナログな対策(運用)を徹底することは、全ての基本です。しかしそれと同時に、人間のパニックや検知の遅れを補い、コンベアを自動で止め、火元だけをピンポイントで叩く先進的なデジタル対策(設備)は、もはや「あれば良いもの」ではなく、「経営を守るための必須の投資」と言えるでしょう。
「まだ大丈夫」と先送りするのか、「明日は我が身」と捉え、今すぐ行動するのか。火災対策とあわせて、火災保険の見直しやBCP(事業継続計画)の策定など、経営的な防御策も併せて検討する時期に来ています。皆様の施設の安全対策を、この機会に今一度見直してみてはいかがでしょうか。
(※1)出典:環境省「リチウム蓄電池等に起因する火災事故等の件数」(2025/6/18発表資料より)
(※2)本記事は「第9回 一般社団法人日本RPF工業会安全大会」の発表内容(提供資料)を基に作成しました。